Blog
|
2025.04.07
Category
Tag
Blog
|
2025.04.07
2025年4月13日から半年間、大阪市の夢洲で開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)。アウトソーシングテクノロジーを含むアウトソーシンググループは、大阪府・大阪市が産官学民で連携しオール大阪で出展する「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」にスペシャルパートナーとして協賛し、同パビリオン内で施設案内などを行う未来のヘルスケアロボ「AIコンシェルジュロボット」を出展する。今回は、開発チームを率いたプロジェクトマネージャー、山本哲也を取材。OSTechだからこそ実現できた、「ヒトと高度なコミュニケーションができるAIを搭載したロボット」の詳細や、開発の苦労話などを語ってもらった。
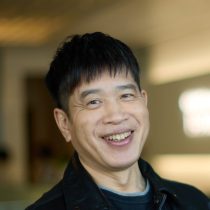
山本 哲也(インテグレーション事業本部 ビジネスデベロップメント室 イノベーションアライアンス課)
◆入社:2023年(中途)
◆趣味:ロードバイク、スキューバダイビング、熱気球
ロボットの見た目は、大型ディスプレイを搭載し、人の身長くらいの高さです。自走式で、さまざまなAI機能を活用することで、来場者に最適な施設案内サービスの提供を実現しました。これを「大阪ヘルスケアパビリオン」内に7台設置。ディスプレイ上に映し出されたAIキャラクター「ミライア・リンクス」が、お手洗いや救護室などパビリオン内の施設までの案内をしてくれたり、おススメの展示内容や当日のイベントを教えてくれたりします。

さらに、「大阪ヘルスケアパビリオン」のコンセプトに合わせて、「特別な装備なしで」血圧や血糖値、血中酸素濃度などを計測し、提示する機能も搭載。非接触バイタルセンシング技術の解析AIによって、顔の画像から生体情報を数十秒で取得することができます。特筆すべきは、多言語に対応していること。世界中からの来場者をお迎えするわけですから、どうしても必要な機能でした。今回、AIキャラクターの声について、プロの声優である佐藤みゆ希さんにご協力いただきました。日本語・英語・中国語・韓国語については、佐藤さんの声でAIが話します。その他にも、フランス語・スペイン語・ポルトガル語・インドネシア語などでもコミュニケーションでき、全人類の8割以上をカバーできるだけの多言語対応能力があります。

ロボットを開発する能力、対人コミュニケーションを可能にするソフトウェア開発能力、たしかなサーバー構築技術、AIを使いこなす技量、新技術を発掘する能力、そしてこれらを統合して1つのコンシェルジュサービスとして確立させるシステムインテグレーション能力を有していることです。これは、ソフトウェアでもハードウェアでも、さまざまなテクノロジーの最前線でエンジニアが活躍し、多様な知見・ノウハウを吸収しているOSTechグループの特長そのものと言えます。
ハードウェアとしてのロボットは、スマートロボティクス社(現在はOSTechのロボティクス技術部)が開発したサイネージロボット。もともと大型のディスプレイを搭載し、街中を動き回って広告する機能をもっていました。そこにAIキャラクターを通して対人コミュニケーションができるよう改造したわけです。
このロボットに「ヒトと関わる仕事をさせる」という「役割」を与えることで、サービスとしての存在価値を設定できなければならない。つまり、求められた要件に対応したコミュニケーションを実現する必要があり、期待された回答を生成できなければなりません。しかし、対人コミュニケーションといっても人間には心を許さずAIになら話せるということもあれば、親近感のない機械のようなものに対して心を開かないという曖昧なところがあります。高性能な生成AI技術で、すべてがなんとかできるわけではありません。ヒトと関わるということは、ASMR(自律感覚絶頂反応)の要素を入れるなど、機械であっても相手であるヒトが共感できる機能が必要です。このため、AI技術を駆使して感情分類やそれと連動したリアクションや音声の発話なども実装されています。
また、万博会場は混雑するでしょうから、「ロボットが自走する」という機能については、十分には真価を発揮しないかもしれません。「ヒトにぶつかりそうになるとストップする」という安全対策が施されているためです。ですが、今後の展開では、「自走」を含めた「自律制御」機能も活きてくると思います。たとえば、「高齢の方や障がいをお持ちの方を見守るためについていって、何かあれば緊急連絡先にSOSを発するロボット」とか、「デパートなどの施設でおススメの商品を紹介しながらルート案内するロボット」とか、さまざまな展開がありえる。今回、万博に出展することで、来場者のみなさんに、こうした可能性を評価していただき、ミライを感じていただきたいですし、OSTechとしても次の展開につながればいいなと思っています。

予測していたとはいえ、最後の最後まで、克服が困難な課題がありました。それは、「相手のしゃべった声を、AIがうまく認識しない」というもの。その原因は、超アナログなところにありました。ロボットの内部では、さまざまな機器が稼働しているので、音声入力という観点でみると「ノイズだらけ」。また、ロボットに搭載されたマイクでは音の反射によって集音がうまくできないということもありました。
そこで「Voice Isolation」というソフトウェアによるノイズ除去を行いました。さらに、ロボットを構成しているハードウェア部品の一つひとつについても解析を行い、有効な対策を行いました。そのような取り組みを重ねた結果、ようやく、実用に耐えうるレベルの音声認識ができるようになりました。
この地道な努力が「報われた」と感じたのは、2025年1月、米ラスベガスで開催された電子機器の世界的な見本市・CESでの経験です。時代はAIエージェント元年と言われ、「対人コミュニケーション能力を備えたアバター」のデモンストレーションがあったのですが、来場者がスタッフから手渡されたハンドマイクを通してロボットと会話しようとしても、うまく認識できていなかったのです。帰国後、このエピソードをメンバーに伝えました。「我々はロボットという厳しい条件下でも音声認識ができる他に類を見ないことに挑戦している」のだと。そして、「我々の生み出したものの精度は高く、我々の仕事は、世界に十分、通用する」と。メンバー全員、とても喜んでいましたね。

キャリアのスタートは米国系総合コンピュータメーカーに入社し、ソフトウェア開発者として半導体工場のMES(製造実行システム)をスクラッチビルドで開発することから、自身のキャリアを積んで10年ほど勤務。最終的にはプロジェクトマネージャーも務めました。その後、米国系ソフトウェア会社にて新製品のプロダクトマネージャーやプロダクトマーケティング、営業支援、テクノロジーアライアンス、市場開発、事業企画など幅広い領域の仕事に取り組みました。
その後も良縁に恵まれてさまざまな機会を得ることになります。IT業界ならではかもしれませんが、「技術要素に精通していること」、「ビジネスのことがわかること」は経歴を重ねるにあたってもっとも評価されたものと思います。そしてOSTechの前職のAIの研究開発会社では、営業責任者として、多方面の企業様に興味をもっていただき、提案を重ね、AIを活用したコミュニケーションサービスを世に送り出すこともできました。
その後、2023年にOSTechへジョイン。国内外で最先端技術を有する新製品の調査から契約締結を担うソーシング担当に着任します。入社とほぼ時同じくして決まった「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」への協賛プロジェクトでは、ロボットを出展するという企画において新規商材を搭載するということとなってコンセプトをまとめる機会をいただきました。その後、開発チームが編成され、前職の経験からチームを率いることになったのです。
私の経験を振り返ると、「最先端の分野に携われる」チャンスは誰にでも必ず巡ってきますし、多くの方が思っている以上にその機会は多いと思います。問題は、その時が来た時に「それがチャンスだと認識できること」、そして「手を挙げられるだけの準備ができている」かどうか。知識を増やし、スキルを高める努力を日頃から続けていなければ、チャンスを掴むことはできません。目の前の仕事から学ぶことも重要ですが、それだけでなく、将来を予測し、目的を持って、特定の業界知識や技術分野、プロダクトに関するコミュニティや勉強会に参加するなど、学び続けてください。「できること」、「わかっていること」を拡げておき、「来たるべきチャンスに備えておくこと」が肝心です。研鑽を重ねることが自身の能力を開花させ、自身の価値を高めていくことにもつながるでしょう。
